SEO
SEO対策は意味がない?やりがちな「やる意味がない」こと、「やってはいけない」こと
- 最終更新日:
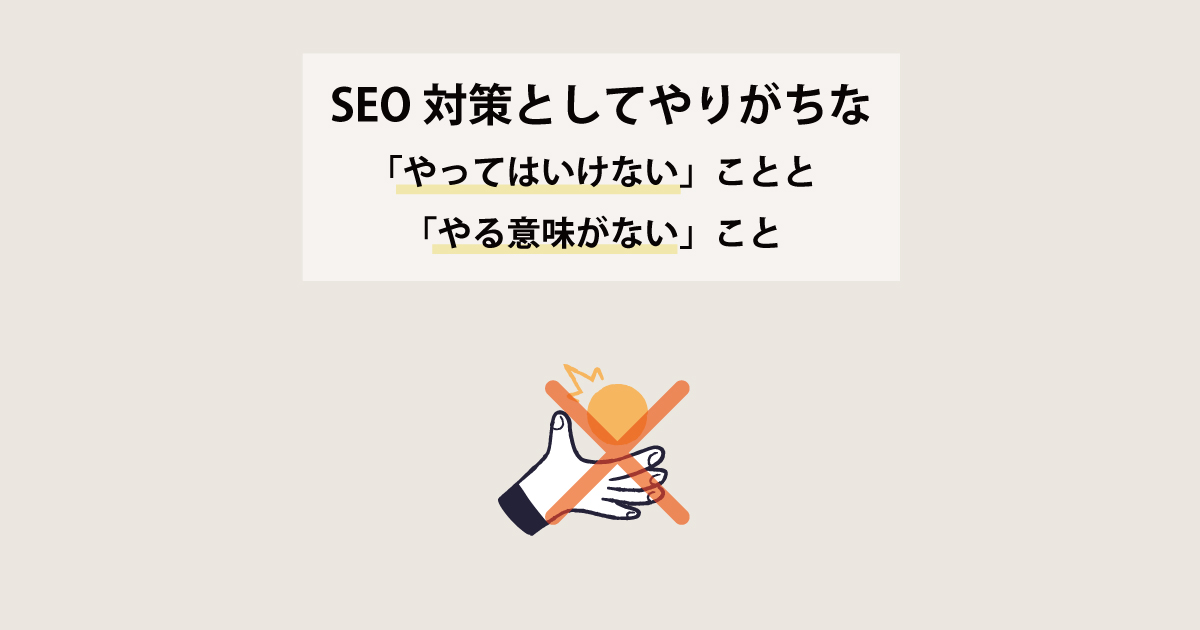
前職でCMSを提供し、1000以上のホームページ運用に関わる経験をしてきた中で、お客様から「検索順位が上がらない」などのSEOに関わる相談を受けることが多くありました。
まず大抵そういうケースは、SEO対策の基本的なことができてないのでそれを改めてお伝えするのですが、「やってはいけないこと」をしてしまっているケースもあります。
この記事では、SEOは意味がない、と感じてしまう方が一定いる事実に対して、そうならないためのポイントについてご紹介するとともに、SEO対策として「やってはいけないこと」とやりがちな「やる意味がないこと」についてもご紹介します。
SEOとは?

そもそもSEOとは何か、よくご存じない方もいらっしゃるかもしれませんので、そこから解説致します。
SEOは「Search Engine Optimization」の略で、日本語で「検索エンジン最適化」の意味です。Yahoo!の検索エンジンにもGoogleが使われているので、それと合わせると日本における検索エンジンの利用率は90%以上がGoogleです。そのためSEO対策は、Google対策とも言えます。
SEO対策は集客に繋がるようなターゲットとするキーワードを定め、そのキーワードでGoogleにおいて検索上位を獲得することを目標とするのが大半です。
SEO対策は意味がない?そう思う人がいる理由
「SEO対策 意味ない」の月間検索ボリュームが720件もあるので、そのターゲットキーワードを狙った記事がたくさんあったりもします(ちなみに当記事もそうです)。
SEO対策は長期的視点に立てば圧倒的費用対効果を生むケースが多いです。実際、当サイトもその状態にできていますので、私は自らそのことを証明してみせています。
では、どうして「SEO対策 意味ない」で検索するのでしょうか?検索意図を考えるというのがSEO記事においては重要です。
以下のような人がいるものと考えます。
- 意味がなかったという話も聞いたことがあるので、未然にそうなることを防ぎたい
- SEO対策をしているが効果が出ない
- 意味がなかったという結果がどのようにあるかを確認することによって意味を確認したい
SEO対策をして意味がないということになってしまうケースというのは大きく4つに分けられます。
そもそも上位を獲得しても流入がないキーワードを狙ってしまっている
そもそも検索ボリュームがない検索クエリ(キーワード)を狙っても、上位を獲得したところで流入は得られません。悪質な業者による、検索ボリュームが少ないキーワードでの上位獲得の提案はよく聞きますので、気をつけましょう。
私の顧客に対して、サイト公開後すぐに難易度の低い検索キーワードでの成果報酬を提案してくる業者がいます。難易度の低い検索キーワードであれば、仮に何もしないでいたとしてもその業者が提示している順位くらいには上がる可能性が高いです。
具体的に何をするのかもわからない検索順位を基準にした成果報酬の提案は、悪質なサービスである可能性が高いので、気を付けてください。
また、そのような業者が絡んでない場合でも、実は検索ボリュームが少ないキーワードを狙ってしまっているケースは案外少なくないかもしれません。
例えば、「地域名 戸建て」の検索ボリュームというのは、どのような地域でも大抵ある程度のボリュームがあって上位獲得の効果はあります。一方で、「地域名 中古車 買取り」の検索ボリュームは、意外にも極端に少なかったりします。「中古車 買取り」の検索ボリュームが月間6万くらいあるにもかかわらずです。この「中古車買い取り」の事業で力を入れるべきなのはSEOよりMEOです。
当方は相談をいただいた結果、SEO対策にコストをかけるべきではない(他の手段にコストをかけるべき)、と判断し、そう提案することがあります。もちろんその時点で料金はいただきません。これが、プライド高き良質で良心的なSEOコンサルタントのやることです。
流入してもコンバージョンに繋がっていない
サイトを見てもらっても、コンバージョン(例えば、問い合わせや購入)に繋がらなければ意味がなかったと感じることになります。
サイトへの流入が増えてくると、サイト全体の評価が高まってくるので、コンバージョンに繋がるキーワードを視野に入れながらであれば、良い傾向になっていると言えます。辛抱強くやるべき、という状況もあるということです。
SEO以外の他の側面で負けているというケースもあります。例えば何かしらの店舗で、すぐ隣により良いサービスで、かつより安いお店があれば、お客さんが比較した結果そちらに流れるのは当然です。両方のサイトを見たうえで問い合わせはそちらに入れられている、というようなケースもあります。やるべきはSEO対策だけではないということも理解しておく必要はあります。
方略は間違ってないが、狙ったキーワードで上位を獲得できない
SEO対策は狙ったキーワードで上位を獲得しにいく活動なので、それが達成できなければ意味がなかった、ということにはなります。
その時点での方略としては大きくは間違ってない場合においても、競合に勝てないケースというのもあります。また、Google(検索エンジン)のアルゴリズムの変更により策略がうまくいかなかった、というケースもあるでしょう。
方略自体が間違っている
かつては、例えばキーワード出現率を高めるなどの小手先のテクニックで検索順位が上がっていました。それが実態だったので、そういう小手先のテクニックはやむを得ず使うしかなかったというのはあるでしょう。しかしGoogleは進歩してますので、現在においては小手先のテクニックは通用しません。
そういう古い知識のままの人というのはかなり多いです。SEOのプロでないため、かつて聞いた知識のままというケースがどうしても多いのと、業者であってもそういう人は多いのが実態です。
以上のうち、1つ目と2つ目は少なくとも良質なSEOコンサルタントが味方に付いていれば防げます。
3つ目のケースはどうしても起こり得ると言えばそうなりますが、優秀なSEOコンサルタントであるほど、そのような結果を生む確率というのは低くなります。
予算内で勝てる戦かどうか、勝ったところで費用対効果があるかどうかを、当方はまず事前に見ます。Googleのアルゴリズムの影響は、もちろんまったくないわけではありませんが、余計なことをしていると影響を受けやすいということもあります。当方はアルゴリズムの影響を受けやすいようなこと(=正攻法ではないこと)はしません。
SEOにおける「プラスの対策」と「マイナスを0にする」対策
SEOには大きく分けて、プラスの加点を得るための対策と、Googleからマイナスの評価を受けないようにする対策があります。
マイナスの評価については、余計なことをしてなければ気にしなくて大丈夫なのですが、「ユーザーに焦点が当たっていない」ことをしている場合、評価を下げられるリスクが非常に高いです。悪質なレベルだとGoogleにみなされればペナルティを受けてしまい、まったく検索に引っかからなくなるという状態になってしまうこともあります。そうなってしまうと、ペナルティを外すために多大なコストがかかります。
「ユーザーに焦点が当たっていない」ことは、SEOとしてもやめるべきなのです。Googleは「ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる」の理念を先頭に掲げています。以前は通用した小手先のテクニックも、技術の進歩によって見破られるようになっています。

やりがちな「やってはいけない」こと
それでは、やりがちな(よく見る)やってはいけないことをご紹介します。
ドメインパワーが強いサイトのサブディレクトリを借りる(寄生サイト/ドメイン貸し)
寄生サイトはおそらく直近で最も流行ってしまっているブラックハットSEOで、目下Googleのアルゴリズムアップデートにより対策が打たれている状況です。
2024年3月のアップデート以降、不正サイトの8割ほどは落とされたという報告を見ます。
サイトはテーマを絞った方が有利で、異なるテーマが混ざると評価が分散してしまうという元々のアルゴリズムもあります。その意味でも貸す側のリスクも非常に大きい対策です。
似たようなテーマであったとしても、異なる事業者だということの判断はある程度Googleは可能でしょうから、おそらくその類のアップデートが行われていると思われます。
重複コンテンツ
他のサイトとコンテンツが重複している場合にGoogleは後から掲載されたコンテンツについて、上位に掲載しないようにします。重複コンテンツがあまりに多いと、サイト全体の評価が下げられてトップページさえ上位に表示されなくなりますし、さらにひどくなるとペナルティを受けることもあるようです。
この重複コンテンツが評価を受けないというのは以前からあったのですが、私の経験的に、ここ最近傾向が強くなっているように思いますので、特に注意してみていく必要があると考えています。
重複コンテンツの具体例
以下に、重複コンテンツの例を挙げます。
コピーしてできたような似たようなサイトを持ってしまっている
検索順位上位の独占を狙ってわざとサイトを複数持つ、ということをしようとしても、独占はできないようになっています。そのようなことをされると、ユーザーはそれぞれを見なくてはいけなくなってしまいますし、両方に同じ内容が掲載されていれば、徒労に終わります。そのようなユーザーのためにならないことは減点対象というわけです。
意図せず古いサイトを残してしまっているケースであっても後から掲載したサイトは順位が上がりません。
他のサイトのコンテンツを真似ている
参考にしている程度の重複なら大丈夫ですが、大量に真似たり、そのままコピーしているようなコンテンツは上位に上がりませんし、大量にあればサイト全体の評価が下がります。
重複コンテンツ扱いの回避策
まったく同じ商品を異なる会社がそれぞれに販売する、ということはよくあります。不動産においても、自社が管理する物件/売却を委託された物件を他社に紹介してもらう、ということはよくあることです。そのような場合、複数のサイトに似たようなコンテンツが掲載されることになりますが、それで問題になったケースは聞いたことがありません。
おそらくは、Googleは以下のようなことを見ていると思います。
- 同一の会社か?(会社情報の一致性)
- 他のサイトからコピーしたような内容か?(タイトル、見出し、その他の文言などが全く同じかどうか)
もしどうしても、自社で複数のサイトに似たようなコンテンツを掲載する場合は、
- 会社概要は両方のサイトに掲載するのではなく、一方のサイトからもう一方のサイトの会社概要にリンクを張る
- 位置づけの違いをタイトル、見出しや、中身の文章で説明する
などしておくのが無難だと思います。ただ、原則としてできるだけ重複コンテンツを掲載するのは避けるべきです。
また、当該ページが評価されることはなくなりますが、それでよければcanonicalタグで正規のページを宣言するという方法があります。当サイトでは以前、トップページの内容と同じ内容でデザインを変えたパターンをデザインサンプルとして示したことがあり、内容自体は重複しているのでcanonicalを使ってトップページが正規であると宣言していました。
同一サイト内での重複について
同一サイト内での重複は、ペナルティを与えられることはおそらくありません。ただ、やはり後から掲載されたページ、ないしは、メインとみなされたページ以外は評価を下げられます。そうでないと、ユーザーが検索した際に、全く同じページが上位を独占するということになってしまいます。
ページに違いがあれば、それを明確に見出し要素「h1」で示すというのがひとつの回避策になります。
ただ、h1だけ異なるページが大量にあるような場合には、評価の分散も起こります。その類のページが1ページしかなければ、そのページに評価が集中するのに対し、似たようなページがたくさんあれば、評価が分散してしまうということです。やはり、ページ内のメインコンテンツはh1の内容に合わせて異なっていないと、なかなかすべてのページが上位に表示されることはありません。
そのあたりも踏まえてどのようにページを用意するか検討するのがよいでしょう。当方は、このようなことも考えての対策を練ることが可能です。
重複コンテンツの調べ方など、重複コンテンツに関してのより詳細な記事も書いてますので、よろしければご参照ください。
被リンクの自作自演
他のサイトからリンクを張られること(被リンク)は、現在でも評価に強い影響があると言われています。このことから、リンクを張るビジネスや、自社でいくつもサイトを作って、評価を受けたいサイトへのリンクを張る、といったことが通用した頃がありましたが、そのようなことをすると現在は、ペナルティを受けてしまいます。
リンクを張られるということは、そのサイトが参考になるということで、信頼性の指標にはなるため、自然と張られるリンクは評価を高めることなります。リンク元のサイトの信頼性が高いほど効果があります。
意図的に張られたリンクであったとしても、知り合いのサイトにリンクを張ってもらうなど、その程度であれば問題にはならないかと思います。評価の高い中古ドメインを買って、そこからリンクを張るという手段もあるようですが、そのサイトの価値を維持することが前提となりますし、そのドメインの履歴、過去の被リンク状態など考えることも多く、簡単な話ではありません。
キーワードの詰め込みすぎ
titleやh1にキーワードを詰め込みすぎると、1つのキーワードに対する評価も分散されて薄まってしまうだけでなく、ユーザーにとってわかりにくい文章になっているとGoogleからペナルティを与えられ、評価を下げられてしまうこともあり得ます。
titleとh1は、ターゲットワードを意識して決めることがとても大事であるとともに、あくまでも、そのページの内容が端的に分かりやすく示されているか、ということも大事です。
titleとh1が何か分からない方はこちらのページをご覧ください。
無用に見出しタグを使っている
見出しタグは効果的に使うことがSEO対策において重要なのですが、そのように強いシグナルを発するタグなので、不適切な使われ方がしていると順位が不自然に落ちることがあります。
次のグラフは、1位と圏外を繰り返すという状態にあったサイトに対して、見出しの使い方を適切にしただけで1位に安定して表示されるようになったという事例です。
このケースは、とある「とても簡単にウェブサイトが作れる」というCMSを使ってノーコードで作られていました。意図せず、ただ文字サイズの調整のためだけに見出しタグがたくさん使われていたというのが原因です。
WordPressは、そういった類のCMSと比べると使い方が難しいと感じる人が多いとは思うのですが、こういうことが防げるUIになっていますし、SEOのことを考えたCMSになっています。

ユーザーにとって価値の低いコンテンツ
例えばアフィリエイトだけを目的にしていたとしても、ユーザーにとって有益な内容であれば上位に表示されますが、ただアフィリエイトはGoogleに目をつけられています。クリックさせることを目的としたサイトという表現で、批判しています。どういうケースが良くないかと言うと、少しスクロールすると広告が表示されるサイトなど最近よく目にするかと思います。見ていて煩わしいですよね?
GoogleはUXをSEOにおいて重視しています。クリックさせることを目的とした設計は、評価をこれからどんどん下げられる方向に向かっていくと私は考えます。
隠しテキスト
以前は、検索キーワードがページ内に多く用いられている方が、単純にそのページが上位にくるようになっていました。その頃に、ユーザーに見えない形で検索キーワードをページに配置するという手法が用いられました。その後、そのようなことをするとペナルティを受けるようになりました。
ペナルティを受ける恐れのある行為としては以下が挙げられます。
- 背景色とテキスト色が同じ
- CSSで画面の外に配置している
- CSSで
font-sizeを0にしている
1か所ある程度ではペナルティは受けないようですが、意図的だと判断される程度に存在するとペナルティを受けることになります。
そもそも、現在は「検索意図に沿っているかどうか」で評価されるので、ペナルティを受けなかったとしても、ユーザーにとって煩わしい内容が多く記載されて評価が上がることはありません。
現在は、仮に検索に用いられたワードがそのページになかったとしても、そのページが検索意図に沿っていれば上位に表示されます。
やりがちな「やる意味がない」こと

Meta keywords(メタキーワード)
「meta keywords」は以下のようにHTMLに記述するもので、以前は意味があったのですが、今はGoogleが意味がないことを明言しています。
<meta name="keywords" content="キーワード1, キーワード2, キーワード3">
今のところ、これを記述しているからといって評価が下げられることはありませんので、あえて書くようにしている業者もみかけますが、もうこのレベルでGoogleが分析することはあり得ないと考えますので、無駄な記述であり、見た人に無知であると思われるのも嫌なので、私は書かないようにしています。
URLに検索キーワードを用いる
URLに検索キーワードを用いた方が良いということを言うSEO業者がいるようですが、少なくともGoogleは関係ないと明言しています。
Google以外でも関係ないという見解が主流ですが、ロシアの検索エンジンであるYandexの過去のアルゴリズムが旧社員により流出する事件があり、ランキングに用いている要素の1つとして「URLに検索キーワードが入っている」というのがあったことは、逆に優秀なSEOコンサルタントには驚きを与えました。ただ流出したアルゴリズムは過去のものが含まれるとYandexが明言しており、今でも関係あるかは分かりません。
ドメイン末尾に何を用いるかを考える
ドメイン末尾に「.co.jp」を用いるとSEOに強いということを言う人がいるようですが、関係ありません。「.com」なのか「.jp」なのか、最近は「.ai」なんてのも見かけますが、あくまでビジネスのために考えれば良いと思いますし、ユーザーはそんなところ気にしないのが実際のところなので、何なら料金で決めてしまっても良いかと思います。
文字数ありきで考える
SEOコンサルタントが良く聞かれる質問第1位ではないかと思うのですが、「1ページあたりの最適な文字数」というのは存在しません。極端な例としてですが、「BringFlowerの電話番号」と検索すれば、端的にそれを示すページが1位に表示されますし、何ならそれより前に正解をGoogleが勝手に示してしまいます。

問題は、検索キーワードの検索意図を満たす内容として、どのくらいのボリュームが必要かであり、無駄な内容ばかりでなかなか必要な情報にたどり着けないようなページは評価は上がらないはずです。検索意図に沿った内容かどうかで評価されます。
端的に示せる内容であればそうした方がユーザーフレンドリーであり、Googleから評価されやすいでしょう。
ただ、誤解が生じやすい理由は、長文コンテンツが必要となる検索キーワードも多いというだけです。例えば「SEO」という検索キーワードで上位を獲得するには、網羅的に広く浅くSEOに関する重要なポイントを示す必要があるので、表示されるページは長文コンテンツばかりです。
E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)が高いように見せかけること
E-E-A-TはGoogleが評価指標として用いているので、影響はあると私は考えていますが、だからといって、E-E-A-Tが高いように見せかけようとしても意味はありません。
サイトの中で事業者情報を充実させたり、記事の執筆者を示すといったことは、サイト閲覧者からの信頼性を得ることに繋がるので、意味はあります。ただし、その中に偽りを書くようなことをしても意味はありません。Googleはそのサイトだけではなく、あらゆるWebページの中から、そのサイトの所有者の信頼性を見極めていることでしょう。
例えば受賞歴があり、その受賞を示すURLがあるような場合は、そこへの発リンクをするようなことをすれば、ユーザーの参考にもなりますし、Googleにとっても参考になるのではないかと考えています。偽りでなければやるべき工夫はあります。
人為的にアクセスを集める
業者の顧客リストに対してメルマガを出してそこからアクセスを集めるといった手法を聞いたことがあります。サイトにアクセスが集まれば、評価がその時に上がる可能性はあるかもしれません。しかし、その対策をやめれば効果がなくなります。一過性の対策にすぎません。SEO対策の大きなメリットは長期的資産になるという点なので、一過性の対策はあまり意味がないと言えるでしょう。
SEO対策においてやるべきこと
ユーザーファースト
Googleが検索エンジンにおいて成功したのはユーザーファーストで考えているからです。Googleで検索したときに、求めている情報が上位に表示されるという状態が作られているからこそ、ユーザーがGoogleを使います。
Googleはユーザーに使ってもらうことで広告収入などを得ていますので、どうすればユーザーの検索意図に合致したコンテンツを上位に表示させられるかに集中しています。
そのために排除すべきコンテンツがあれば排除をするわけです。
E-E-A-Tを高める
E-E-A-Tは経験(Experience)、専門性(Expertise)、権威性(Authoritativeness)、信頼性(Authoritativeness)の略で、Googleは信頼性が認められる記事を上位に表示するために、記事執筆者の経験、専門性、権威性を評価軸として用いています。
例えば提示する情報の根拠となる情報を引用リンク付きで示すなど、知っておくことで出来る対策はあります。詳しくは次の記事をご参照ください。
SEOの評価軸の1つ「E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)」とは?高める方法も紹介
どの専門性についてGoogleに評価してもらうのか、サイトのテーマを定め、その専門性をGoogleに認めてもらえるような記事を書いていきましょう。
ChatGPTを用いるより10倍早く、かつ最大限にその能力を引き出すBringRitera(リテラ)の利用がおすすめです。
コーディングの品質を高める
titleタグ、h1タグなど、SEOのためには外せないコーディングが存在します。SEO対策をアピールしているにもかかわらず、それさえもまともにできてない事例は多く見ます。このような業者を見抜くのは難しいですが、その方法は後ほどご紹介します。
titleタグ、h1タグなど、SEOのためには外せないコーディングが存在し、SEO対策をアピールしているにもかかわらず、それさえもまともにできてない事例は多く見ます。このような業者を見抜くのは難しいですが、見極め方をこの後ご紹介します。
SEO業者の品質の見極め方

品質の高い業者であれば、その業者自身のサイトが上位に表示されているはずです。当サイトのように。
SEO業者の言い分は、「SEOをやれば利益に繋がる」ですよね?
であれば、まず自社がそれに取り組むはずです。自社が利益に繋がるサイトを構築できてないのに、顧客にSEOを提案するというのは、不思議ではないでしょうか?
良い業者の探し方は、ウェブで検索して上位に表示される業者の中から探すというやり方です。それで見つかるということは、SEO対策ができているということなので、外れは引きにくいと思います。
悪質なことを提案する業者の名前を聞いて、その業者のことを検索して調べてみると、案の定自サイトのSEO対策ができていません。
被リンク集めやアクセスを集めるといった手法は水物ですが、コンテンツSEOは、コンテンツが残り続けるので、長期的な視点で見れば大きな費用対効果に繋がります。当サイトはそうなっていますし、大きな資産となっています。
次の記事は、Googleによるものです。
以下の項目があります。こちらもあわせてご確認いただいても良いでしょう。
- 不審なメールを送信する SEO 業者、ウェブ コンサルタント、代理店にご注意ください。
- Google で一番上に掲載されることは誰にも保証できません。
- 隠し立てする会社や、行動の目的を明確に説明しない会社には、用心してください。
- SEO 業者にリンクする必要は一切ありません。
- 賢明な選択が求められます。
- SEO 業者との契約を検討する際は、業界について調査することをおすすめします。もちろん、Google を使うのも 1 つの方法です。Google では、特定の業者については言及しませんが、これまで遭遇した会社の中には、SEO 業者と名乗りながら、認められるビジネス行為の範囲を明らかに超えた行為を行っている業者もあります。くれぐれもご注意ください。
- 何に対して料金を支払うのかを確認しましょう。
- その他の注意点をチェックします。
まとめ
Googleは検索エンジン最適化スターターガイド(英語版)を最近更新して、そこの中でもこの種の紹介がされています。
SEO対策の基本は、ユーザーにとって有益なコンテンツをつくることです。具体的な施策についてのご相談はこちらからお願いします。









